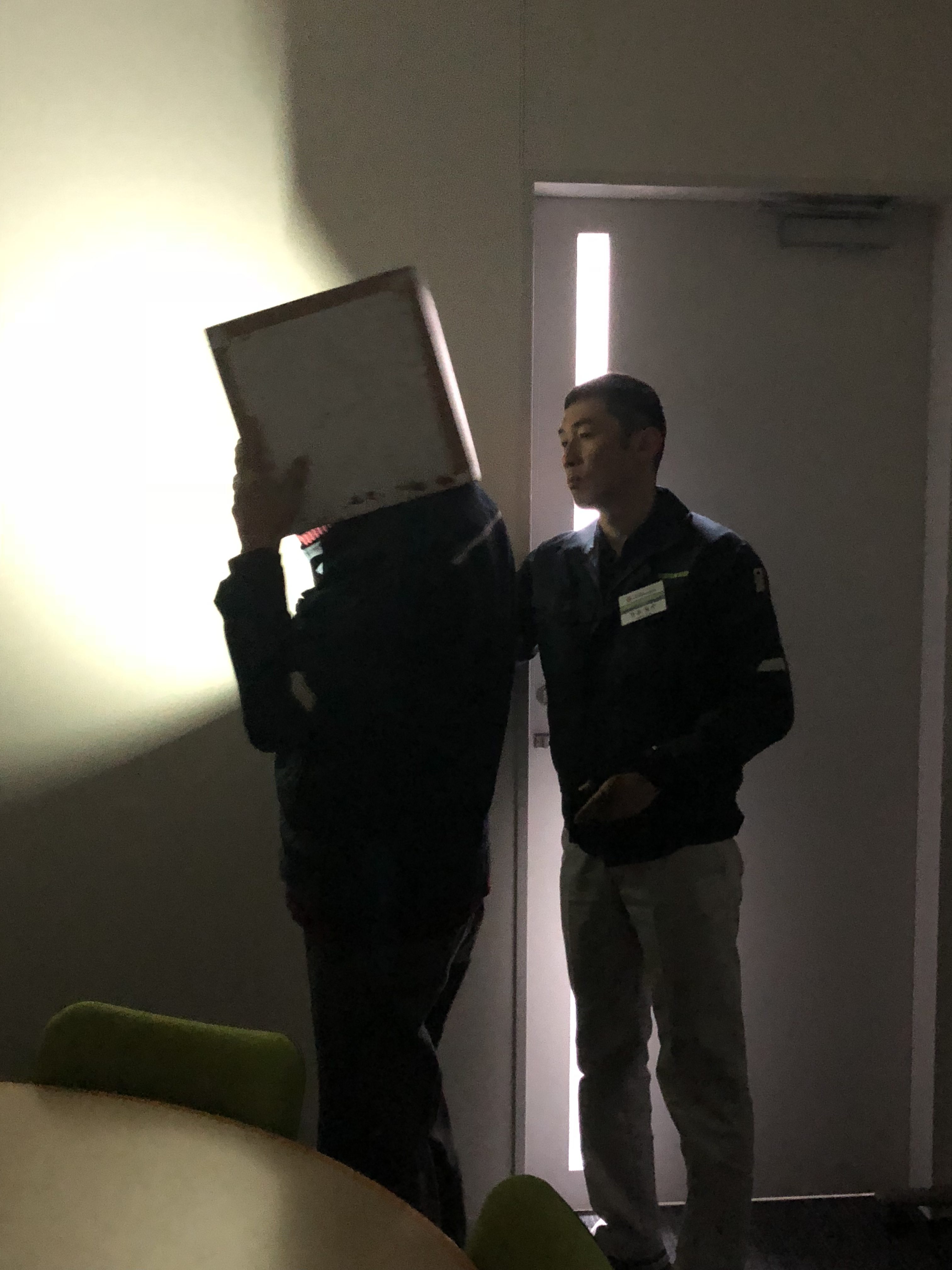【企画:漆芸】戸田蓉子【建築設計】佐藤研也 (studio Niko/東京藝術大学COI拠点)
【認知科学スタディ】竹浪祐介 (京都市産業技術研究所)
内部総黒漆仕上げ 移動組み立て式茶室空間 1800㎜×1800㎜×1800㎜
金閣寺の金箔張り替えに携わった職人の「全面に黒漆を塗りこめた空間に立った時、上下左右がわからなくなり自分がどこに立っているのかわからないような不思議な感覚を覚えた」という言葉から着想を得た。これは金閣三層目「究竟頂」内部の金箔を貼る前の、六面すべて漆黒の状態を指した言葉と思われる。
「漆黒」という色の価値は日本独特の美としてその深みや艶により周知されている。昭和30年代から合成漆器なるものが登場し、現代では精度の上がったバイオプラスチックが開発されている。では命ある漆の木の樹液、生き物である本当の漆の質感とは?漆の美とは?漆の力とは?漆芸に携わる者として「本当の漆黒」の価値を再構築し人々に認識してもらう必要があると切に感じ、当プロジェクトを企画した。
また、この漆黒の面が感覚器官に与える効果を現代の認知科学の見地から検証解明することをも、このプロジェクトでは目的とする。作品として制作された漆黒空間はまた、実験装置としても機能する。
建築的見地からは、現代のデジタル技術のデータでもって作った小屋に、伝統的な手仕事で魂を込めた漆の壁を組み込むことで空間を完成する。塗るという行為は空間を変容させることである。
漆黒の中で、自分自身というミクロコスモスと対話し、また自身を包む宇宙というマクロコスモスへと思いを馳せるような、精神にはたらきかける空間をも目指す。なぜなら漆は、縄文時代の遺跡から出土する神事や呪術に用いられた朱塗りの櫛や道具、中世の仏教寺院の什器根来を見てもわかるように、歴史の中で人間の精神に寄り添ってきた素材だからである。
さらに、日本には古来から、神を移動させるという独特の感覚がある。それは式年遷宮や、仏像を移動する際に魂を抜いてまた戻すという行為に顕著である。私たちは現代においてこの漆黒の中にある何を運ぶのだろうか。空間をたたみ、またどこかの地で空間を再現する度に。この空間に入ってくれるビジターとともにそれを考え作り上げていくことができれば、それにまさる喜びはないと考える。
【協力】木村宗慎(茶人、作家)
【制作協力】@カマタ
“Jet-black space project” (temporary title)
Direction, Lacquer: Yohko Toda
Architectural design: Kenya Sato 〈Studio Niko〉
Study of cognitive science: Yusuke Takeura
Mobile collapsible tea room/ Interior finished with Kuro Urushi (black lacquer)
“When I stood in the space covered with Kuro Urushi, I suddenly felt disoriented and was overcome with a mysterious sensation of losing where I was standing. ”
This work is inspired by the words of a gilding artisan who was engaged in the restoration of Kinkakuji Temple. It is assumed that this artisan worked on the third level called The Cupola of the Ultimate (Kukkyou-chou) and the words describe the room coated in jet-black Urushi before gilding the walls and ceiling completely with gold leaf.
First, in this work, we will study the effects of black walls on the eyes from the aspect of contemporary cognitive science. Then applying the knowledge acquired, we plan to build a space where one can re-experience the awe of the artisan mentioned above. We will utilize the latest digital technology to design and construct the tea room. The construction will be complete with the integration of the walls finished with utmost care and traditional craftsmanship using Urushi. The final touch with black Urushi breaks down the physical boundaries enabling a metaphysical sense of ascension.
As we can see from examples of red Urushi lacquered combs and magico-religious instruments from the Jomon-period, and negoro-ware and furniture from medieval Buddist temples, Urushi has been in close relationship with the human psyche from the earliest times. This space aims to influence the mind through encouraging self-dialogue, interacting with the inner micro-cosmos and to expanding one’s consciousness to the surrounding universe as the macro-cosmos.
From the ancient times, Japan has a unique custom of periodically moving around objects of worship. The Shikinen Sengu (Ise Shrine transfers their deity to an entirely new shrine every 20 years) and moving a Buddha statue (they first extract the soul and then after, restore it) are good examples. So in this endeavor, what can I transfer to this world every time I collapse and erect this jet-black space? I am excited to contemplate and co-create this with the visitors.
cooperation:Soshin Kimura(tea master,essayist)
Production cooeration:@Kamata